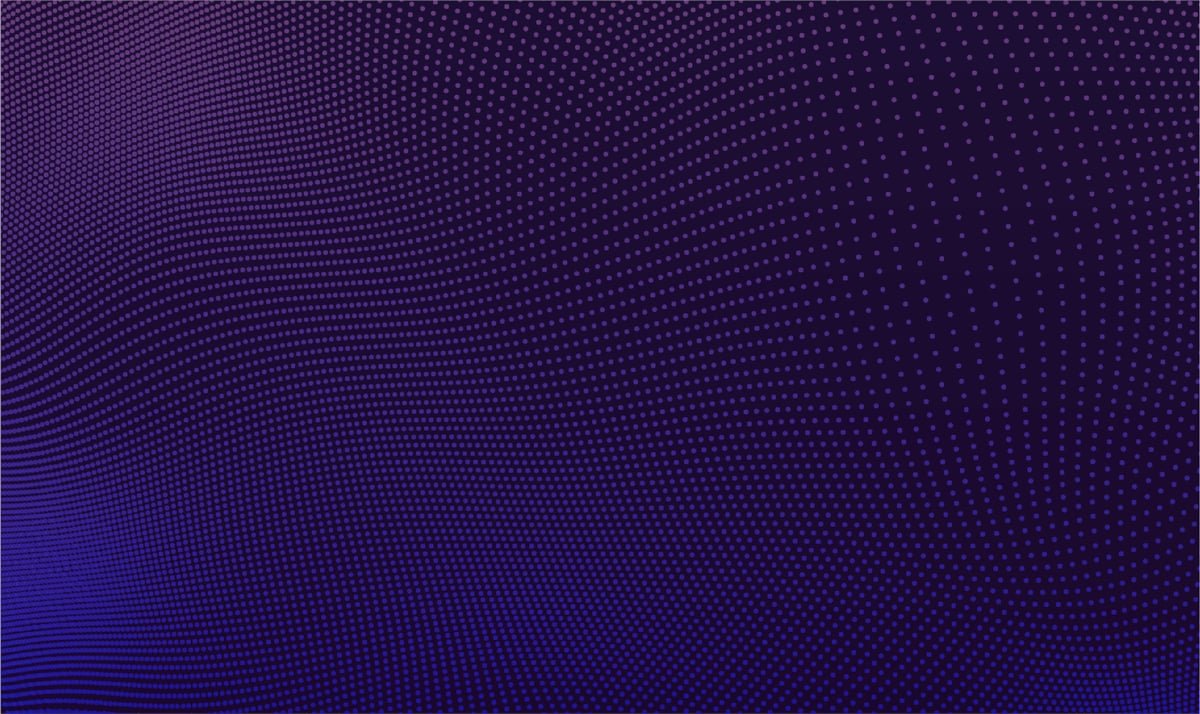SERVICES
私たちの主なサービス
-

相続税申告
豊富な知識と経験を活かして、総合的な相続税申告サービスを提供いたします。豊富な知識と経験を活かして、総合的な相続税申告サービスを提供いたします。
-

M&Aコンサルティング
M&AのトータルアドバイザーとしてM&Aの売手サイド・買手サイドの立場から税務・財務・法務の知識を駆使してサポートいたします。M&AのトータルアドバイザーとしてM&Aの売手サイド・買手サイドの立場から税務・財務・法務の知識を駆使してサポートいたします。
-
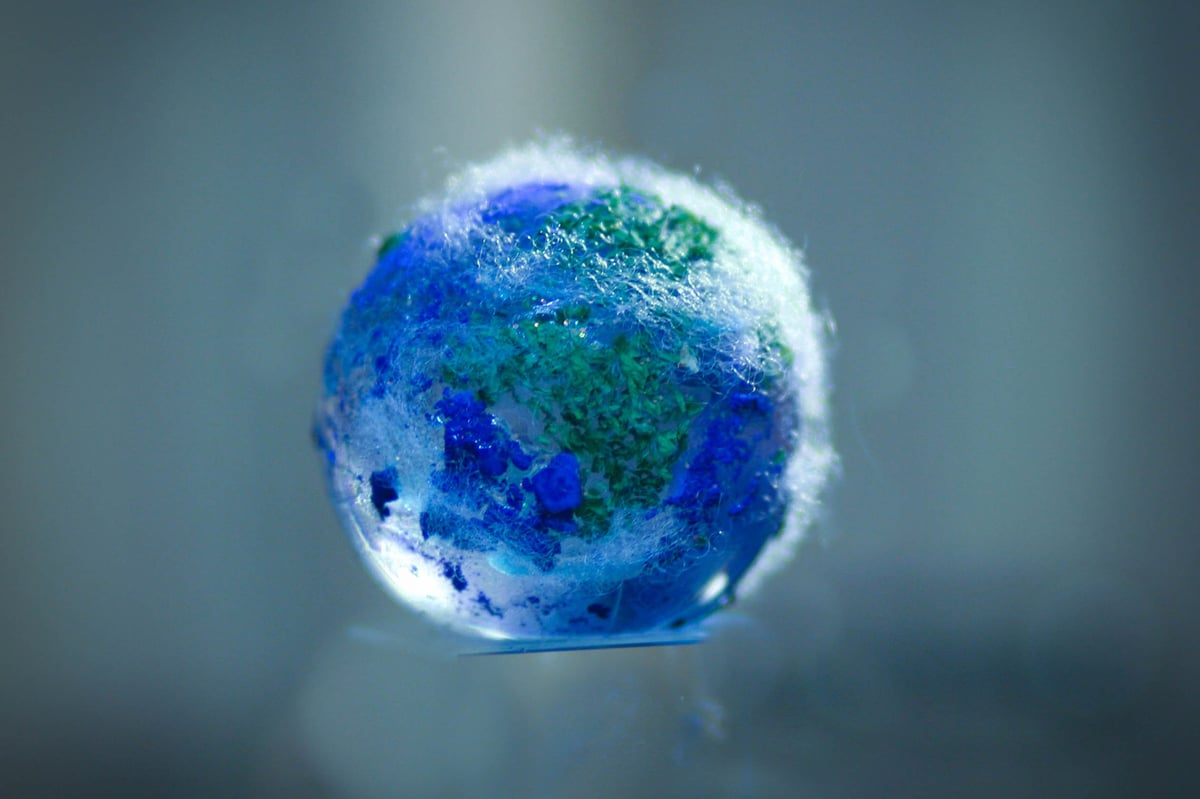
国際相続業務
国際相続の専門チームのメンバーと連携してお客様のニーズにお応えします。国際相続の専門チームのメンバーと連携してお客様のニーズにお応えします。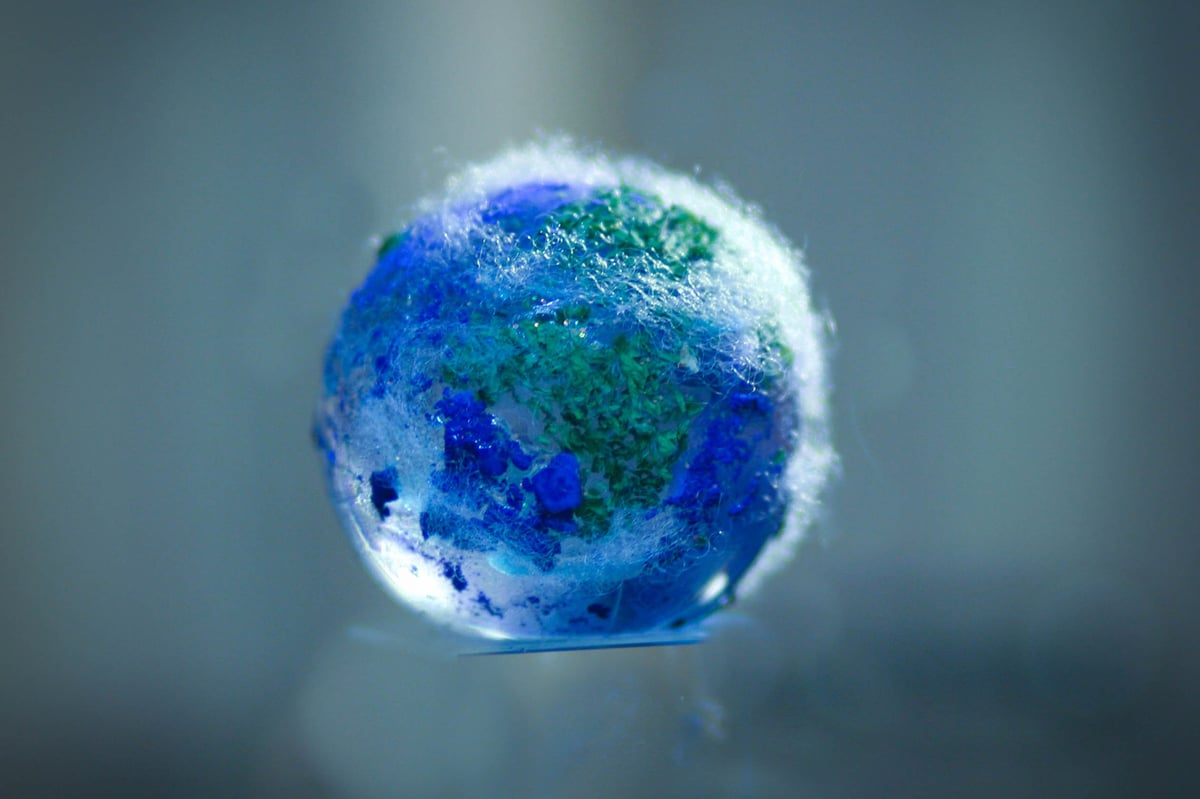
-

認定医療法人コンサルティング
医療法人移行する方に向けてコンサルティングを提供いたします。医療法人移行する方に向けてコンサルティングを提供いたします。
SEMINAR
オンラインセミナー
セミナーを開催しております。専門家による最新情報を踏まえた解説をご活用ください。
-
受付中

2024年4月26日(金)15:00 〜 16:00
海外子会社資本再編時における実務上の留意点 —税務を含む日本国内の手続きとアセアン、グレーターチャイナ、アメリカを中心として—
TOPICS
おすすめのトピックス
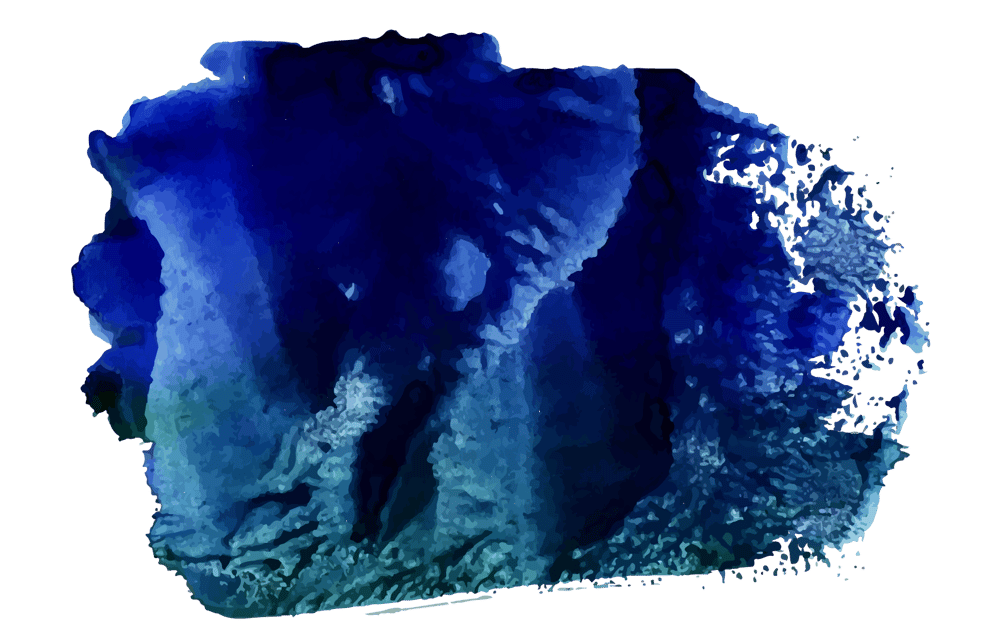
CONTACT US
弊社へのご質問、ご依頼、ご相談など
各種お問い合わせはこちらにご連絡ください。